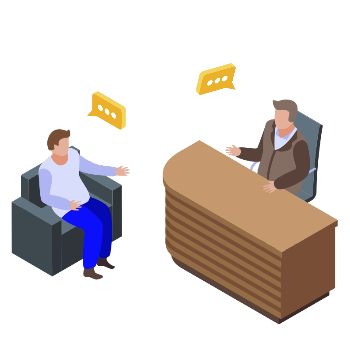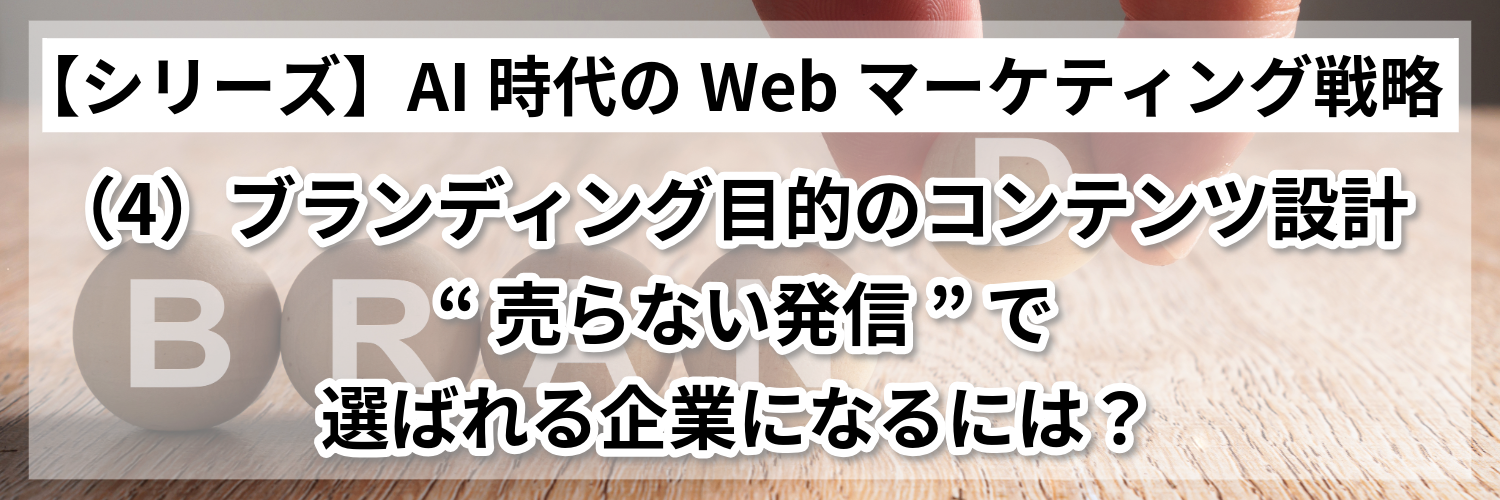
更新日:2025/8/1
AI時代に企業が選ばれるためには、短期的な売上を追わない「ブランディング目的の発信」が不可欠です。これにより、AIとユーザー双方に「信頼され、愛される関係性」を築くことが、中長期的な成果に繋がります。
本コラムでは、AI時代になぜブランディング目的の発信が重要なのかを解説し、具体的な目的別のコンテンツ設計視点、そして効果的なチャネル設計とコンテンツ連携の方法を実践的にひも解いていきます。
★コラムを音声で読む(準備中)
本コラムでは、AI時代になぜブランディング目的の発信が重要なのかを解説し、具体的な目的別のコンテンツ設計視点、そして効果的なチャネル設計とコンテンツ連携の方法を実践的にひも解いていきます。
★コラムを音声で読む(準備中)
なぜ今、「売らない発信」であるブランディングが必要なのか
「検索されないなら、ブランディングコンテンツは意味がない」と考えてしまうのは早計です。むしろ今こそ、AI時代における企業の存在感を示すために、ブランディング目的の発信がかつてないほど重要になっています。
有名なブランディング手法に、企業名やロゴを繰り返し見せることで消費者の信頼や親しみを醸成する「単純接触効果」を活かしたテレビCMなどがあります。こうした接触型の広報活動は今も有効ですが、情報接触の場がWebやSNSに移行した現代では、“文脈ある接触”がより重要になっています。
なぜなら、ユーザーは「自ら探して比較する」より、「出合った情報の中から、なんとなく良さそうなものを選ぶ」傾向が強まっているからです。この“なんとなく良さそう”という印象を形づくるのが、企業の姿勢や発信の一貫性であり、ブランドの印象なのです。
さらに、AIやレコメンドアルゴリズムもまた、「誰が、どんなテーマで、どれだけ継続的に発信しているか」といった情報の“文脈”を加味して情報を提示するようになっています。単発でバズるよりも、積み重ねられた発信の一貫性や信頼性が、“AIにとっても信頼できる情報源”として評価される要因になります。
つまり、AI時代におけるブランディングは「人に信頼される」ための発信であると同時に、「AIに選ばれる」ための土台づくりでもあるのです。
発信がぼやけるのは「目的」が不明確だから
売上に直結しないブランディング目的のWebコンテンツでは、「何を伝えたいか」は明確でも、「誰に・なぜ伝えるか」が曖昧なまま制作されていることがあります。結果として、トーンやメッセージがぶれ、コンテンツ同士に一貫性がなく、読者の印象に残らないものになりがちです。
ブランディング目的のコンテンツにおいては、まず「目的の言語化」が最優先です。
- 信頼を得たいのか?
- 共感を集めたいのか?
- 親しみを感じてもらいたいのか?
- 専門性・誠実さを感じてもらいたいのか?
目的に応じたブランディングコンテンツの設計視点
ここでは、「目的の言語化」で明確にした軸に基づき、代表的な4つの目的に応じたコンテンツタイプと設計のヒントを紹介します。
-
信頼を得たい:企業の姿勢や価値観がにじむコンテンツ
代表や社員へのインタビュー、ビジョンを語るコラム、取り組み事例の紹介など
ポイント:単なる情報提供ではなく、「なぜこの考え方を大切にしているのか」を丁寧に掘り下げることで、“この会社は誠実だ”という印象を持たれやすくなります。
- 共感を集めたい:ストーリー・人を中心に据えたコンテンツ
顧客とのエピソード、社内の裏話、挑戦や失敗談など
ポイント:「自分ごと」として読者が感情移入できる内容が理想です。文章よりも動画・SNS投稿などの形式とも相性が良いです。
- 親しみを持ってもらいたい:“中の人”発信やキャラクター活用
X(旧Twitter)での中の人日記、Instagramでの日常投稿、ライブ配信など
ポイント:コンテンツそのものよりも“語り手の人柄”が鍵になります。継続的な発信で関係性を深める設計が効果的です。
- 専門性・誠実さを見せたい:実務に役立つ情報提供型コンテンツ
ホワイトペーパー、Q&A記事、ハウツー解説、業界トピックへの見解など
ポイント:実務者にとって「読んで得した」と思える内容であることが大事。検索だけでなくSNSやメルマガとの連携も有効です。
ブランディングを「届ける」チャネル設計とコンテンツ連携
どんなに良いコンテンツがあっても、届け方を誤ると読まれません。
検索だけに依存しない今、ブランディング目的の発信においてはSNS・メルマガ・動画などとの複合的な連携が鍵になります。
- note:理念・思想系の長文に強く、SNSシェアとも相性が良い
- メルマガ:親密な関係性を育てる“ファン向けチャネル”として活用
- SNS(X/Instagram):共感・拡散を狙える場。トーンとビジュアルが重要
- YouTube:ストーリー性のある企業紹介や、イベント動画、現場の裏側紹介に
| コンテンツタイプ | 主な目的 | 有効なチャネル |
|---|---|---|
| インタビュー/思想記事 | 共感・信頼の醸成 | note/メルマガ |
| 無償情報コンテンツ | 専門性×誠実さ | オウンドメディア |
| ストーリー型事例 | 好感・親しみ | SNS/動画 |
| 対話型コンテンツ | 関係構築 | SNS/Live配信 |
| “中の人”発信 | 企業の人格化 | X/note/LinkedIn |
【まとめ】AI時代は“好き”と“信頼”が選ばれる理由になる
ユーザーが企業を選ぶ基準は、情報の正確さや機能性だけではありません。「この会社、なんか好き」「信頼できそう」と感じる感情的な接点が、大きな差別化要因になりつつあります。
こうした共感や信頼の積み重ねが“ファン”を生み、いずれは受け取った情報を熱心に語ってくれる、ブランドの応援者になってくれるかもしれません。
“好き”と“信頼”、そして“共にありたいと思える関係性”を育む発信こそが、AIにもユーザーにも選ばれるブランディング戦略なのです。
よくある質問(FAQ)
ブランディングコンテンツの成果はどうやってKPI化すればいい?
PVやCVでは測れないため、「ブランド想起率の変化」「SNSでの好意的コメント」「メルマガの開封率」など、接触の質や再接触行動をKPIとするとよいでしょう。
BtoB企業にとってのブランディング発信の効果とは?
決裁者の多くは企業文化や誠実さに共感して発注を決めています。Web上の信頼資産(実績、発信内容、人物像)を積み上げることで、商談前から“信用される土壌”をつくれます。
社員によるSNS発信の進め方がわかりません。社内の理解も薄いです。
「何を・どこまで話していいのか」を明確にするガイドラインを設けた上で、社内勉強会やロールモデル紹介を通じて徐々に土壌を育てるのが有効です。
ブランディングコンテンツはどんなテーマから始めればいい?
「自社がなぜこの事業をしているのか」「どんな価値を届けたいのか」など、理念や背景にフォーカスしたコンテンツが初手に適しています。代表インタビューや創業ストーリーが特におすすめです。
売上に直結しないブランディング発信に対して、社内理解が得られません。
AI時代では「売らない発信」こそが信頼形成とブランド構築に欠かせません。PVやCVだけでは測れない価値があることを、目的と指標をセットで社内に共有することが重要です。成果が見えづらいからこそ、継続的な姿勢と共感の蓄積が中長期的な競争力になります。
関連コラム
お問い合わせ
お電話またはメールフォームより、
お気軽にお問い合わせください。
お気軽にお問い合わせください。
03-5784-0702
受付時間 / 10:00~19:00