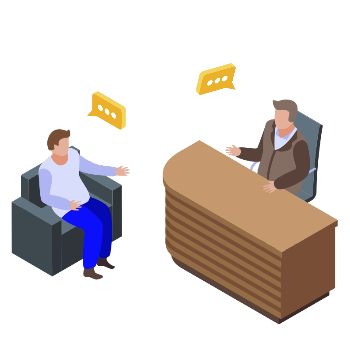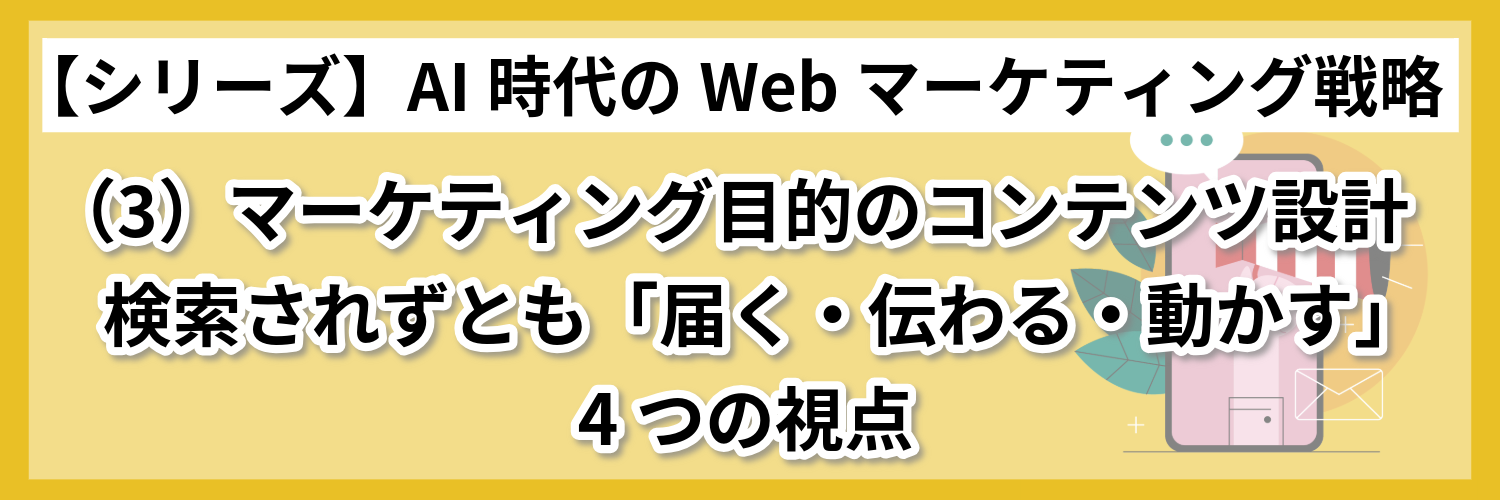
更新日:2025/7/29
AI時代にマーケティング目的のコンテンツで成果を出すには、「検索される」のを待つだけでなく、読者の行動まで見据えた「読みたくなる設計」「拡散される設計」「引きつける設計」「見つけてもらう設計」という4つの視点での設計が不可欠です。
本コラムで詳しくご紹介します。
★コラムを音声で読む(準備中)
本コラムで詳しくご紹介します。
★コラムを音声で読む(準備中)
【視点1】読みたくなる設計:要約されても興味が続く構成に
AIによる要約は、コンテンツの入口として機能する一方で、要約だけで満足されてしまうリスクもあります。マーケティング目的においては、要約によって概要が伝わったあとに「その先を読みたくなる」仕掛けを設けることが重要です。
たとえば、以下のような設計が有効です:
- 要約では拾われにくい“文脈”や“感情”を含める
商品の開発背景、顧客のリアルな声、課題に直面した場面の描写など、人間味のあるストーリーや深みのある情報が、読者の興味を引きつけます。
- 記事冒頭に問いかけや診断コンテンツを置く
「あなたの悩みはAタイプ?Bタイプ?最適な解決策をチェック」のように、読者自身が”自分で選択して結果を受け取る”形式は参加型であり、本文への強い導線となります。
- 判断に迷いが生じやすいポイントで商品の「背景」や「意図」を丁寧に補足する
なぜこのサービスを選ぶべきなのか、導入の決め手となる視点など、読者の疑問に寄り添う情報が深掘りを促します。
つまり、要約されることを前提にしつつ、「要約では伝えきれないものが本文にある」と思わせる構成が大切です。
特に、診断コンテンツのように読者自身が「自分で選択して結果を受け取る」形式は、参加型でありながら結果に応じた深掘り記事や商品紹介に自然につなげやすいという利点があります。
【視点2】拡散される設計:SNSと連動した話題性と共感性
SNSは、マーケティング目的のコンテンツにおいて“届けたい人に確実に届ける”ための最重要チャネルの一つです。検索流入が減少する中、SNSは自発的な検索を必要とせずに、ユーザーの関心に応じてコンテンツがレコメンドされる場でもあります。
つまり、検索されなくても“見つけてもらえる”可能性があるという点で、SNSとの連携は集客設計の根幹になります。
SNSで拡散されるコンテンツには、“共感”と“親和性”が不可欠です。投稿文が単なる紹介文で終わるのではなく、記事との対話になっていることで、クリック率やシェア率が大きく変わります。
以下のような工夫が有効です:
- SNS投稿文に「問いかけ」や「共感ワード」を盛り込む
「#Web担当あるある」「◯◯な人に読んでほしい」「忙しいママにこそ知ってほしい時短アイテム」など、ターゲットの心に響く言葉を選びましょう。
- 記事導入部にSNSでそのまま使えるキャッチフレーズを置く
「Web担当者なら共感必至の“読まれない問題”、どう突破する?」「3分でわかる、今すぐできる乾燥肌対策」など、短いフレーズで興味を引きます。
- SNS上のトレンドや話題と記事内容を結びつける
最近のAI活用事例、季節商品やライフイベントとの連動など、タイムリーな話題とコンテンツを結びつけましょう。
こうした設計により、投稿文と記事が“会話”し、読者の興味を引き出す接点になります。
【視点3】引きつける設計:ビジュアルで直感に訴える
マーケティング目的のコンテンツでは、まず"見つけてもらう・開いてもらう"ことがスタートです。
その接点を担うのが、サムネイルやビジュアル。SNSやレコメンド経由では、ユーザーが視覚的な第一印象で「読むか・スルーするか」を瞬時に判断するため、ここが最大の勝負どころです。
視覚的な訴求力は単なる装飾ではなく、認知や興味を引き出すための"入り口設計"なのです。
サムネイルやビジュアルで引きつけるには:
- タイトルに連動した、キャッチコピー入りの画像を作成する
- 人物写真や手書き風アイコンなどで"人感"を加えることで、親しみや共感を誘発する
- ブランドカラーやフォント、レイアウトをテンプレート化し、統一感を出すことで"誰の発信か"をひと目で伝える
- 複数パターンを作ってA/Bテストを行う
- スマホ表示を前提に「小さくても伝わる」ビジュアルを心がける
「読ませる」以前に「見つけてもらう」ことが、マーケティングの勝負を決める第一歩です。
【視点4】見つけてもらう設計:検索されなくてもユーザーに「届く」仕組みづくり
検索に頼らない情報接触が一般化する中で、Webコンテンツは「検索されるもの」から「届けられるもの」へと変わりつつあります。Google DiscoverやX(旧Twitter)、ニュースアプリ、企業メルマガ、自社サイト内の関連記事など、さまざまな“非検索経由”の接点で記事がレコメンドされる機会が増えています。
このような環境でコンテンツを届けるために意識したいポイント:
- レコメンド文脈に沿ったタイトル&導入文
検索キーワードではなく、ユーザーの関心や行動文脈にマッチするタイトルを設計しましょう。「◯◯が気になる人向けの新常識」のように、読者の潜在的なニーズに響くタイトルは、レコメンドでの接点を創出します。
- 記事冒頭で「なぜ今この情報が必要なのか」を明確に提示
レコメンドエンジンは“クリック後の滞在率”も判断材料にするため、読者にすぐに価値を伝えることが重要です。
- 構造化されたデータや正確なメタ情報の整備
Google Discoverなどでは技術的要素も影響するため、適切な技術的SEOが不可欠です。
- 他チャネルからの流入導線を設計
SNSやメルマガなど、検索以外のチャネルでコンテンツがシェアされやすい見出しやビジュアルを併用し、初速を意識した流入導線を設計しましょう。
【まとめ】設計しないコンテンツは、もう誰にも届かない
AIやSNSが情報流通の主導権を握る今、コンテンツは「検索される」から「届けられる」ものへと変化しています。マーケティング目的の発信には、単なる情報提供を超えた“設計”が求められます。
「読みたくなる構成」、「拡散を促すSNS連携」、「視覚で引きつけるビジュアル」、そして「読後の行動を促す導線」。
この4つの視点を意識すれば、検索に依存せず、必要な相手に“届く・伝わる・動かす”コンテンツが実現できます。
よくある質問(FAQ)
記事を作っても検索流入が増えません。何が問題?
検索ニーズが減少傾向にある中で、検索以外の流入経路(SNSやレコメンド)を設計に組み込むことが重要です。
SNSに投稿してもクリックされません。どうすれば?
投稿文と記事の導入文を連動させ、「読者の悩みに寄り添う」メッセージ設計が効果的です。
AIに要約されると伝えたい内容が省略されてしまいます。対策は?
体験談や感情を含むストーリー形式にすることで、要約されにくくなります。
どんなサムネイルがクリックされやすい?
キャッチコピー入り・人物写真入り・ブランドカラー使用など、「目を引く」ビジュアル設計が有効です。
読者参加型コンテンツって何が効果的?
診断系やチェックリスト形式のコンテンツは、自分ごととして関心を引きやすく、滞在時間も伸びやすいです。
関連コラム
お問い合わせ
お電話またはメールフォームより、
お気軽にお問い合わせください。
お気軽にお問い合わせください。
03-5784-0702
受付時間 / 10:00~19:00